倉知淳が奏でる「ABC」の変奏
倉知淳は、その巧妙なプロット構築と、ロジックとユーモアを絶妙に融合させる作風で知られる、現代日本ミステリ界でも特異な立ち位置を占める作家である。彼が手掛けた短編『変奏曲・ABCの殺人』は、その真骨頂を示す傑作として語られるべき作品である。初出は『月刊ジェイ・ノベル』2011年3月号であり、後に短編集『豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件』に収録された 。
この短編集自体が、SF風味の作品からユーモアミステリ、そして本格ミステリまでを収めた、まさに「本格ミステリの玉手箱」と評される多様性に富んだ一冊であり、『変奏曲・ABCの殺人』はその中でも特に強烈な個性を放っている 。
出典:amazon.co.jp
本稿では、この『変奏曲・ABCの殺人』の核心に迫るため、物語のあらすじ、登場人物、そして結末のどんでん返しに至るまで、完全なネタバレを含む徹底的な解説と考察を行う。未読の方は、作品の驚きを損なう可能性があるため、注意されたい。本稿の目的は、単なるあらすじの紹介ではなく、倉知淳がいかにしてミステリの古典的題材を解体し、再構築したか、その技巧の深層を明らかにすることにある。
この作品を理解する上で最も重要な鍵は、そのタイトルにある。「ABCの殺人」という部分は、ミステリファンならば誰もがアガサ・クリスティーの不朽の名作を想起するだろう。しかし、その前に置かれた「変奏曲(Hensoukyoku / Variations)」という言葉こそが、本作の本質を指し示している。
音楽における変奏曲とは、一つの主題(テーマ)を基に、旋律、和声、リズムなどを変化させて新たな楽曲を展開する形式である。倉知淳は、クリスティーが確立した「ABC殺人」という主題を用い、それを現代的な視点から大胆に変奏してみせる。これは、単なるオマージュやパロディに留まらない、原作の構造そのものに対する批評的かつ知的な応答なのである。読者はこのタイトルによって、初めから作品をメタ的な視点で読み解くよう誘われるのだ。
第一章:原典『ABC殺人事件』の構造と本作品の着眼点
倉知淳による「変奏」の巧みさを十全に理解するためには、まずその原典であるアガサ・クリスティーの『ABC殺人事件』の構造を把握しておく必要がある。クリスティーのこの長編は、ミステリ史における金字塔の一つである。
出典:amazon.co.jp
物語は、名探偵エルキュール・ポワロのもとに「A.B.C.」と名乗る人物から挑戦状が届くところから始まる 。予告通り、アルファベット順に指定された地名で、同じイニシャルの名前を持つ人物が次々と殺害されていく 。アンドーヴァー(Andover)でアリス・アッシャー(Alice Ascher)が、ベクスヒル(Bexhill)でベティ・バーナード(Betty Barnard)が、といった具合に犯行は続き、現場には必ず「ABC鉄道案内」が残されている 。
この連続殺人は一見、無差別な狂人の犯行に見える。しかし、ポワロが最終的に暴き出す真相は、その見立てを根底から覆すものであった。一連のアルファベット殺人は、実は犯人が本当に殺したかったたった一人の人物(Cの被害者)の殺害を、無差別殺人という壮大なカモフラージュの中に紛れ込ませるための、極めて合理的な計画だったのである。つまり、『ABC殺人事件』の核心は、「無秩序に見える連続殺人の背後に、一つの合理的な殺意が隠されている」という構造的トリックにある。
これに対し、倉知淳の『変奏曲・ABCの殺人』は、物語の開始時点から全く異なるアプローチを取る。本作は、犯人の視点から物語が語られる「倒叙形式(インバーテッド・ミステリ)」を採用しているのである 。読者は探偵と共に謎を追うのではなく、犯人の内面に入り込み、その計画の遂行を内側から見つめることになる。この形式の選択こそが、本作のテーマを際立たせるための最も重要な構造的決断であった。
倒叙形式によって、読者が直面する謎は「誰が犯人か(Whodunit)」から「犯人は計画を成功させられるのか(Will he get away with it?)」へとシフトする。我々は、主人公である犯人の身勝手で歪んだ論理を追体験させられる 。そして、この物語がもたらす最終的な衝撃は、犯人の「完璧な計画」が内側から崩壊していく様を目の当たりにすることから生まれる。
その恐怖は、殺人鬼の正体を知る恐怖ではなく、主人公が信じていた世界の法則が根本的に間違っており、現実は彼が想像するよりも遥かに混沌としていると気づかされる、哲学的・心理的な恐怖なのである。この形式は、読者を一時的に犯人の視点に同化させることで、結末のツイストがもたらす「世界観の崩壊」という衝撃を最大化させるための、極めて効果的な装置として機能している。
第二章:詳細なあらすじ(完全ネタバレ):自己中心的な男の完全犯罪計画
物語は、主人公である段田富士夫(だんだ ふじお)の視点から始まる。彼は、自身の弟である高志(たかし)を心底から疎ましく思っており、その殺害を計画している。動機は金銭的なものも示唆されるが、それ以上に彼の根底にあるのは、弟に対する身勝手な軽蔑と自己中心的な思考である 。
そんなある日、世間では奇妙な連続殺人事件が話題となっていた。
- 最初の事件(A):足立区青原(あおはら)の路上で、浅嶺久美(あさみね くみ)という女性が殺害される。
- 次の事件(B):足立区番祥寺(ばんしょうじ)の家屋で、馬場茂昭(ばば しげあき)という男性が殺害される 。
地名と被害者のイニシャルが「A」「B」と続いていることに、メディアは飛びつき、世間は「ABC殺人鬼」の出現に騒然となる。このニュースを目にした富士夫は、自身の計画にとって千載一遇の好機が訪れたと確信する。彼の住まいは台東区堂ヶ谷(どうがや)。弟の高志を殺害すれば、それは見事に「D」の事件となる。世間で進行中の連続殺人に便乗し、弟の死を連続殺人鬼の犯行に見せかける。これこそが、彼が思い描いた完全犯罪の青写真であった 。
富士夫は、計画の「D」を実行する前に、第三の事件「C」が起こるのを辛抱強く待つ。しかし、待てど暮らせど「C」の事件は一向に発生しない。焦燥と傲慢さに駆られた彼は、ついに自ら行動を起こすことを決意する。「流れが滞っているのなら、自分で作ればいい」。彼は「C」に合致する格好の標的を見つけ出し、自らの手で第三の殺人を実行する。これで舞台は整った。A、B、そして自らが作り出したC。この流れに乗ってDを実行すれば、自身の犯行は完全に連続殺人の中に埋没するはずであった 。
この時点での富士夫の認識と、物語の客観的な事実の間には、致命的な乖離が存在する。以下の表は、その構造を視覚的に整理したものである。
| A | 事件: 足立区青原・浅嶺久美 | 認識: 連続殺人の第一の犯行。計画の着想源。 | Aの殺人事件が発生した。Bとの関連性はメディアが作り上げた憶測に過ぎない。 |
| B | 事件: 足立区番祥寺・馬場茂昭 | 認識: 連続殺人の第二の犯行。計画を確信。 | Bの殺人事件が発生した。パターンが存在するという確証はどこにもない。 |
| C | 計画&事件: (該当者なし) → 自ら実行 | 認識: 計画を進行させるための必要悪。自らの手で「流れ」を作る。 | 富士夫が殺人を犯す。彼は連続殺人を継続していると信じているが、実際には孤立した殺人犯が独自の「パターン」を捏造しているに過ぎない。 |
| D | 計画: 弟・高志を殺害 | 認識: 計画の最終目標。連続殺人犯の犯行として処理されるはずの完全犯罪。 | 富士夫個人の、単一の動機に基づく殺人の標的。 |
この表が示すように、富士夫の計画は「AとBの事件が同一犯による連続殺人である」という、証明されていない前提の上に成り立っている。彼はメディアが作り出した物語を信じ込み、その虚構の舞台の上で自らの犯罪を演じようとしているのである。この根本的な誤認こそが、彼の計画を破滅へと導くことになる。
第三章:結末の皮肉と恐怖:「人を呪わば穴二つ」の現代的解釈
自ら「C」の殺人を遂行し、いよいよ弟・高志を手に掛ける「D」の段階へと駒を進めた段田富士夫。彼の計画は最終段階に入ったはずであった。しかし、まさにその時、物語は読者の予想を裏切る、皮肉に満ちた驚愕の展開を迎える。
テレビのニュース速報が、新たな殺人事件の発生を告げる。それは「D」の事件であった。だが、一つではない。次から次へと、全く別の場所で、全く別の犯人による「D」のイニシャルを持つ被害者の事件が報じられ始めるのである 。富士夫が完璧に設えたはずの舞台は、突如として無数の模倣犯、あるいは彼と同じような思考を持つ便乗犯たちによって溢れかえってしまった。彼の計画は、刑事の鋭い推理によって阻止されたのではない。それは、社会の混沌とした現実そのものによって、無意味で滑稽なものへと成り果てたのだ。
この結末は、まさに「人を呪わば穴二つ」ということわざを現代的に解釈したものである 。連続殺人という「パターン」の中に隠れ、捕食者として振る舞おうとした富士夫は、今や自らがその名( 段田・Danda)ゆえに、自分が作り出したわけでも制御できるわけでもない、新たな恐怖のパターンの中に放り込まれた一人の潜在的な被害者となってしまった 。彼は、自分が仕掛けた罠に自らが絡め取られるという、究極の皮肉に直面する。この結末は、一部の読者には「すっきりする展開」と映るかもしれないが、よく考えると「怖い結末」であり、なんとも複雑な読後感を残す 。書評家が「死角からぶん殴られたような衝撃」と表現したように、読者は犯人の視点に立っていたからこそ、この世界観の反転を強烈な一撃として体験するのである 。
ここに、倉知淳の仕掛けた「二重の逆転」というべき、本作の最も優れた洞察がある。クリスティーの原典は、「狂人の無差別殺人」という見せかけ(カオス)を逆転させ、その背後に「合理的な単独犯の計画」(オーダー)を明らかにすることで読者を驚かせた。倉知淳は、その構造をさらに逆転させる。主人公の富士夫は、クリスティー作品の犯人と同じように、連続殺人というオーダーを利用して自らの合理的な犯行を隠そうとする。しかし、物語の最終的なツイストが暴き出すのは、そもそも彼が利用しようとした「AとBの連続殺人」というオーダー自体が存在しなかった、という事実である。
AとBの事件は、おそらく何の関係もない、それぞれ独立した偶発的な事件だったのだろう。それを「連続殺人」という物語に仕立て上げたのは、センセーショナルな物語を求めるメディアと、それに踊らされる大衆の想像力であった。富士夫は、存在しない秩序を利用しようとした結果、破滅する。
本作における真の敵対者は、名探偵ではない。それは、予測不能な人間の悪意が同時に多発する「混沌(カオス)」そのものである。クリスティーが混沌の中に隠された秩序を見出したのに対し、倉知は、人々が秩序だと信じているものこそが、実は混沌の現れに過ぎないと喝破する。これは、情報(あるいは誤情報)が現実を規定し、存在しないパターンを人々に信じ込ませてしまう現代社会に対する、極めて冷笑的で鋭い批評となっている。
第四章:作品考察:倒叙形式、ブラックユーモア、そして社会風刺
『変奏曲・ABCの殺人』は、その緻密なプロットを通して、複数のレベルで機能する多層的な物語である。
第一に、技術的なミステリとして、本作は倒叙形式をいかに効果的に使って読者に驚きを与えるかという点において、一つの到達点を示している。犯人の視点に読者を固定することで、犯人自身が気づいていない情報の欠落や世界の真の姿を隠蔽し、最後の瞬間にそれを突きつける手法は見事である。
第二に、ブラックユーモアの作品として、本作は痛烈な可笑しさを内包している。そのユーモアは、主人公の計画が失敗する様に宿る、宇宙的な皮肉から生まれる。自らの知性を過信し、完璧な犯罪者であると自惚れていた男が、より優れた知性によってではなく、単なる偶然と、自分以外の人間にも存在するありふれた悪意の統計的な奔流によって打ち負かされる。この展開は、滑稽であると同時に恐ろしい。このユーモアと恐怖のブレンドは、本作が収録された短編集全体の「とぼけたユーモア」や「上質な皮肉」といったトーンとも共鳴している 。
第三に、社会風刺として、本作は現代社会に蔓延する自己愛(ナルシシズム)と、「自分は特別である」という幻想に対する鋭い批判となっている。富士夫は、自分の犯罪計画が天才的なものであると信じて疑わない。しかし、結末が明らかにするのは、彼の「輝かしいアイデア」が、実は驚くほど陳腐で、他の多くの人間も思いつくような凡庸なものであったという事実である。
この物語は、メディアに煽られ、誰もが物語の主人公になりたがる現代の「メインキャラクター症候群」を風刺している。富士夫は、歴史に残る犯罪者になるどころか、恐るべき社会現象を構成する、名もなきデータの一つに過ぎなかったのである。そのプロットは、テレビ番組「世にも奇妙な物語」を彷彿とさせる、日常に潜む奇妙さと恐怖を描き出している 。
興味深いのは、本作に対する読者の評価が二分している点である。ある読者は「オチもまぁ読めます」と結末の予測可能性を指摘し、「人を呪わば穴二つ」という教訓的な枠組みを読み取っている 。一方で、プロの書評家は「死角からぶん殴られたような衝撃」を感じている 。この一見矛盾した反応は、作品の欠陥ではなく、むしろその多層的な構造を反映した特徴と捉えるべきである。
この物語は、二つのレベルで同時に機能している。
一つは、「悪事を企む者は、いずれ自分に返ってくる」という、寓話的で道徳的なレベルである。この観点から見れば、結末は確かに「予測可能」な範疇にある。
もう一つは、「その破滅が、いかにして訪れるか」という、プロットのメカニズムに関わる知的でスリリングなレベルである。富士夫の破滅をもたらすのが、名探偵の論理ではなく、無数の凡庸な悪意の同時多発という統計的な恐怖であるという点は、決して予測容易ではない。読者がどちらのレベルにより強く反応するかによって、作品から受ける印象は「予測可能な教訓譚」にも「衝撃的なスリラー」にもなり得る。
倉知淳の技巧は、この両方の読者を満足させる懐の深さにある。道徳的な結末という安心感を与えながら、その実現方法においては知的な衝撃を与える。この二重性こそが、本作を単なるアイデア一発の小品から、繰り返し考察に値する作品へと昇華させているのである。
結論:ミステリの定石を逆手に取った倉知淳の技巧
倉知淳の『変奏曲・ABCの殺人』は、単なる名作のパロディやオマージュという評価を遥かに超える、極めて洗練された文学的装置である。それは、ミステリの古典的な定石(トロフィー)を発射台として用いながら、現代社会の病理に対するダークで、ユーモラスで、そして深く不穏な批評を展開する。
倉知淳の作家としての卓越した技術は、本作の隅々にまで見て取れる。犯人の視点を用いる倒叙形式を完璧に使いこなし、読者の認識を巧みに誘導するプロット構築能力。そして、知的興奮と本能的な恐怖を同時に呼び起こす物語を編み上げる筆力。これら全てが結実した本作は、短編ミステリという形式でしか到達し得ない、凝縮された完成度を誇っている。
最終的にこの物語が我々に突きつけるのは、秩序を装う混沌の姿であり、個人の悪意がいかに容易に社会全体のノイズの中に埋没し、また同時にそのノイズを形成するかという、現代的な真実である。書評家が倉知淳の作品群を評して用いた「知の刺激」や「緻密な推理とロジックが描く予想外のシュプール」という言葉は、まさに本作にこそふさわしい 。
『変奏曲・ABCの殺人』は、同じ短編集の表題作『豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件』がそうであるように、一見すると奇抜でユーモラスな設定から出発し、それを冷徹な論理で貫き通すことで、読者に忘れがたい知的衝撃を与える。倉知淳の技巧と悪戯心が見事に結実した、現代短編ミステリの小さな傑作であると言えるだろう。
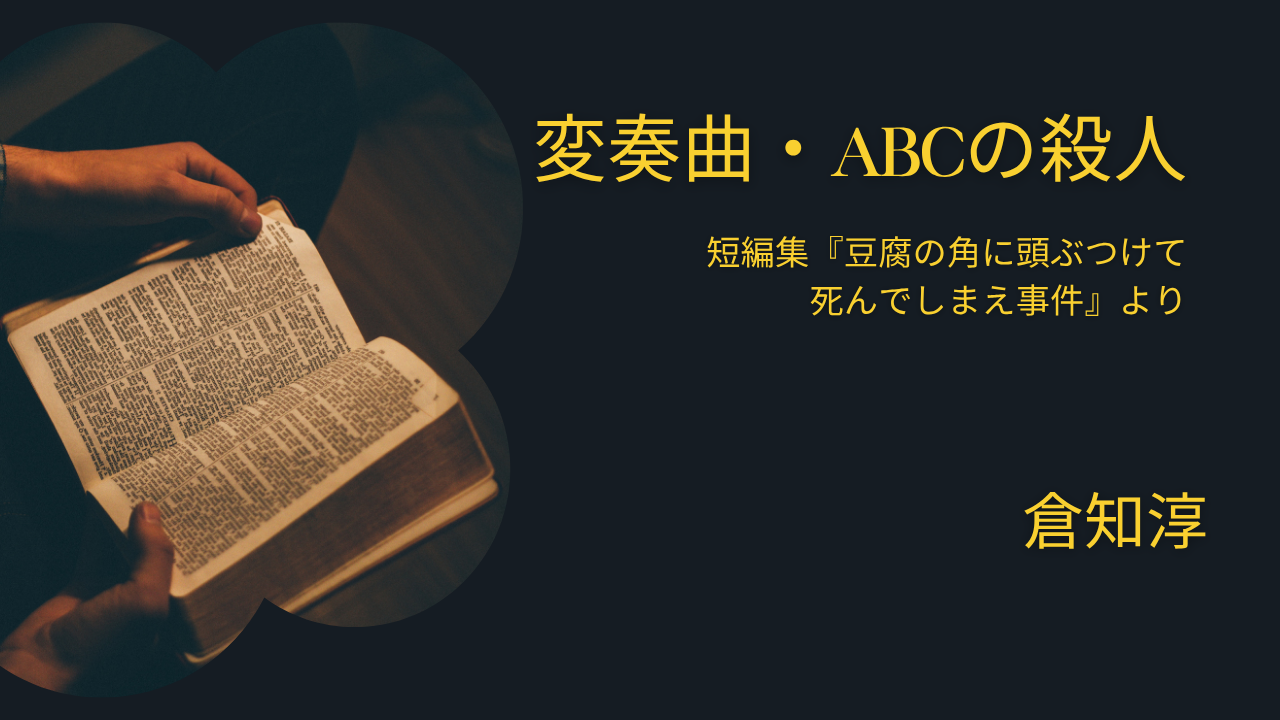
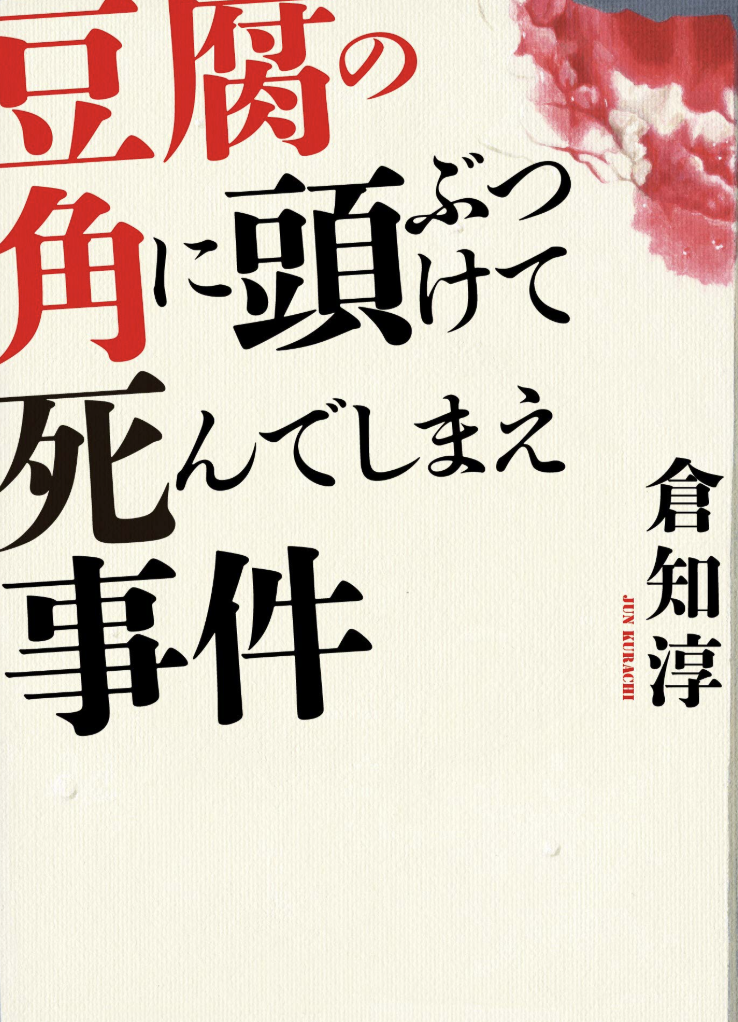
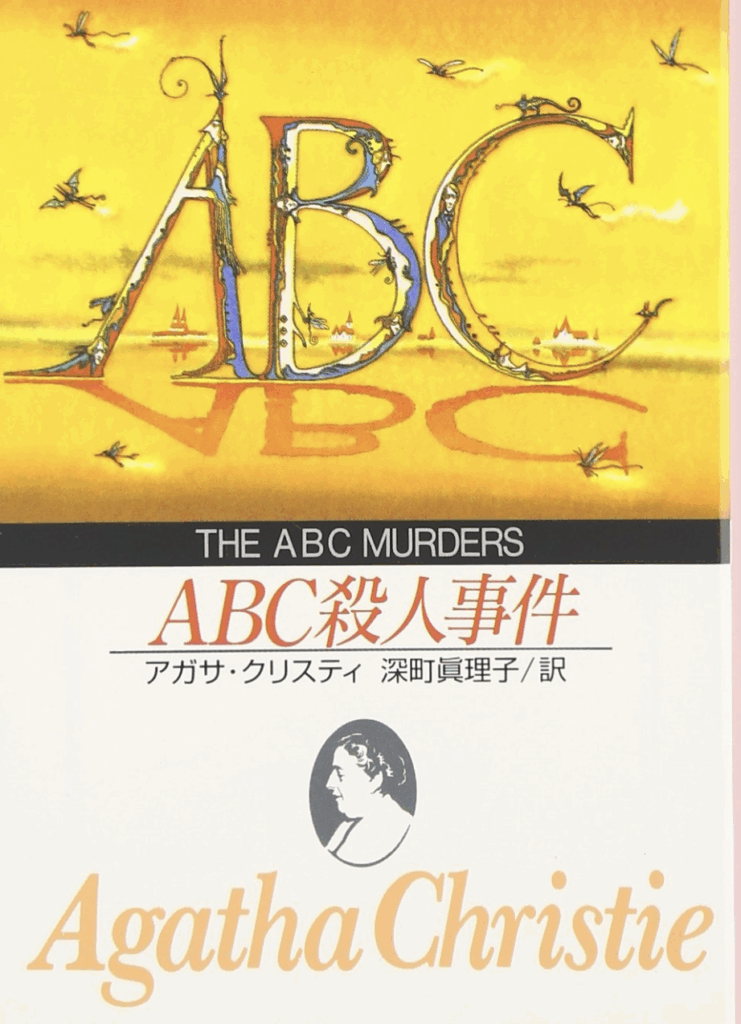
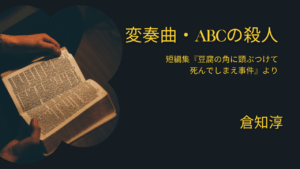
コメント