ジュール・ヴェルヌの『地底旅行』を初めて読んだとき、私は驚いた。
映画『地底探検』(1959)の印象が強烈だったからだ。
映画では、物語の序盤で学者が何者かに殺害され、主人公たちも命を狙われる。緊迫したサスペンスが全編を貫く。ところが原作には、そのような要素がほとんどない。
なぜハリウッドは、純粋な科学冒険小説に「殺人事件」を挿入したのか。この改変は単なる娯楽性の追求だったのか、それとも何か必然性があったのか。
原作の「静かな冒険」
ヴェルヌの原作『地底旅行』(1864)は、実に穏やかな物語だ。主人公アクセルの視点で語られる一人称の語りは、知的好奇心と懐疑心のバランスが取れている。
物語は、ハンブルクの鉱物学者リーデンブロック教授が、古い羊皮紙に書かれた暗号文を発見するところから始まる。それを解読すると、16世紀の錬金術師アルネ・サクヌッセムが、アイスランドの火山からヨーロッパまで地底を旅したという内容だった。教授は甥のアクセルとともに、この旅を追体験しようと決意する。
注目すべきは、原作には明確な「敵」が存在しないことだ。リーデンブロック教授、アクセル、そしてアイスランド人ガイドのハンスの三人は、渇き、迷路、地底の嵐といった自然の脅威と戦う。しかし、彼らの探検を妨害する人間は登場しない。サクヌッセム本人も、すでに何百年も前に死んでいる。彼は後続者を妨げる「敵」ではなく、むしろ道を照らす「先駆者」として描かれる。
この構造は、19世紀の科学冒険小説としては極めて健全だ。敵は人間ではなく、未知の自然そのもの。勝利とは、他者を打ち負かすことではなく、知識を獲得して生還することだ。
映画が追加した「ゲタボルグ教授の死」
ところが1959年の映画版では、物語の構造が根本的に変わる。
映画では、リンデンブロック教授がサクヌッセムの手がかりを発見すると、すぐにスウェーデンの地質学者ゲタボルグ教授に手紙を送る。このゲタボルグ教授は原作には存在しない、完全なオリジナルキャラクターだ。そして、リンデンブロック教授がスウェーデンに到着すると、ゲタボルグはすでに何者かに殺害されている。
この殺人事件の犯人として登場するのが、サクヌッセム伯爵——サクヌッセムの子孫を名乗る男だ。彼は、先祖の発見を独占し、自分だけが地底世界の秘密を手に入れるべきだと考えている。伯爵はリンデンブロック一行を執拗に追跡し、彼らの探検を妨害し続ける。
つまり、映画は「人間対自然」という原作の構造を、「人間対人間」という対立に書き換えたのだ。
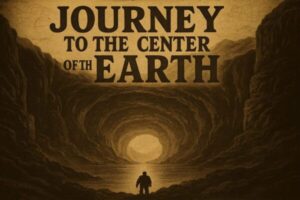
なぜハリウッドは「敵」を必要としたのか
この改変には、1950年代のハリウッド映画の文法が深く関わっている。
当時の娯楽映画、特に大作冒険活劇には、明確な善悪の対立が求められた。観客は、応援すべきヒーローと憎むべき悪役を欲していた。単に「自然の困難を克服する」だけでは、2時間の映画としてドラマ性が不足すると判断されたのだろう。
さらに、テレビの普及という背景も無視できない。1950年代後半、家庭にテレビが急速に浸透し、映画館の観客動員数は減少していた。映画産業は、「テレビでは味わえない体験」を提供する必要があった。その答えの一つが、シネマスコープという横長フォーマットであり、もう一つが、より刺激的でサスペンスフルな物語構成だった。
ゲタボルグ教授の殺害シーンは、映画の冒頭近くに配置される。これは観客に「この探検には命の危険がある」という緊張感を早期に植え付ける効果がある。以降、画面外に潜む「敵」の存在が、観客の不安を煽り続ける。サクヌッセム伯爵がいつ現れるか分からないという恐怖が、地底探検そのものの驚異と並行して展開されるのだ。
「発見の競争」という新しいテーマ
興味深いのは、この改変が単なるサスペンス要素の追加に留まらず、物語のテーマそのものを変容させたことだ。
原作の『地底旅行』は、科学的発見の「共有」を前提としている。リーデンブロック教授は、旅から帰還した後、自らの発見を学会で発表し、世界中に知らしめる。知識は人類共通の財産であり、独占すべきものではない——これが、19世紀啓蒙主義的な科学観だった。
ところが映画版では、「発見の独占」という欲望が前面に出る。サクヌッセム伯爵は、先祖の発見を自分だけの財産として守ろうとする。一方、リンデンブロック教授は、科学の進歩のためにその秘密を公開しようとする。両者の対立は、「科学的探求心 vs. 利己的な独占欲」という道徳的対立として描かれる。
これは、冷戦時代のアメリカ社会が抱えていた価値観を反映している。1950年代、科学技術は国家間の競争の道具となっていた。スプートニク・ショック(1957年)によって、アメリカは宇宙開発競争でソ連に遅れをとっていることを痛感した。「発見」は、もはや純粋な知的好奇心の産物ではなく、国家の威信をかけた戦いの対象だった。
映画『地底探検』における「発見の競争」という構図は、こうした時代の空気を色濃く反映している。
「殺人」が生み出す道徳的正当性
さらに重要なのは、殺人事件の導入が、主人公たちの探検に「道徳的正当性」を与えたことだ。
原作では、リーデンブロック教授の探検動機は純粋に個人的な好奇心だ。彼は名誉欲も持っているが、基本的には「知りたいから行く」という単純な動機で行動する。これは19世紀的な探検家の典型的な姿だった。
しかし1950年代のハリウッド映画において、主人公の動機は常に「正義」と結びついている必要があった。単なる好奇心や冒険心だけでは、観客の共感を得にくい。主人公は、何か「正しいこと」のために行動していなければならなかった。
ゲタボルグ教授の殺害は、この問題を一挙に解決する。リンデンブロック教授たちは、もはや単なる冒険家ではない。彼らは、殺害された同僚の遺志を継ぎ、悪しき独占者から科学的発見を守る「正義の使者」となる。探検は、個人的な興味の追求ではなく、道徳的使命となるのだ。
これは、ハリウッド的な物語構造の典型だ。西部劇では主人公の家族が悪党に殺され、それが復讐の旅の動機となる。戦争映画では仲間の死が、戦いを続ける理由となる。『地底探検』もまた、この古典的なパターンを踏襲している。
カーラ・ゲタボルグという存在
この改変によって生まれたもう一人の重要人物が、ゲタボルグ教授の未亡人カーラだ。
原作には女性は登場しない(厳密には、アクセルの婚約者グラウベンが地上で待っているが、彼女は旅には同行しない)。リーデンブロック教授、アクセル、ハンスの三人による男だけの探検だ。これは19世紀の冒険小説では一般的な構成だった。
ところが映画では、カーラが探検隊に加わる。彼女の動機は、夫を殺した犯人を突き止めること、そして夫の遺志を継ぐことだ。つまり彼女もまた、「殺人事件」によって物語に巻き込まれた人物なのだ。
カーラの存在は、1950年代のハリウッド映画における「ヒロイン」の役割を果たす。彼女はロマンスの相手であり、危機に陥ることで救出のドラマを生み出し、男性キャラクターたちの保護本能を刺激する。これらはすべて、当時の商業映画の定石だった。
しかし同時に、カーラは殺人事件の被害者の遺族として、物語に感情的な深みを与える役割も担っている。彼女の存在によって、ゲタボルグ教授の死は単なる事件ではなく、人間的な悲劇として観客に届く。映画全体に流れるサスペンスは、単なるスリルではなく、彼女の復讐と正義の追求という個人的なドラマと結びつくのだ。
原作と映画、どちらが「正しい」のか
ここで一つの問いが浮かぶ。原作の静かな冒険と、映画の刺激的なサスペンス、どちらが「正しい」形なのか。
もちろん、これに絶対的な答えはない。文学と映画は異なるメディアであり、それぞれに最適な物語構造がある。19世紀の読者は、内省的で教養的な長文の旅行記を楽しんだ。一方、1950年代の映画観客は、視覚的な刺激と明確なドラマを求めた。
原作の美点は、その純粋さにある。ヴェルヌが描くのは、人間の知的好奇心の力だ。未知への憧れ、発見の喜び、困難を克服する勇気——これらが、人間対人間の争いに汚されることなく描かれる。
一方、映画の美点は、その普遍性にある。ゲタボルグ教授の殺害とサクヌッセム伯爵の登場によって、物語は「善と悪」「正義と欲望」という誰もが理解できる構図を獲得する。これは、より広い観客層に物語を届けるための、必然的な選択だった。
改変の代償——失われたもの
ただし、この改変には代償もあった。
原作の魅力の一つは、アクセルの内面の成長だ。臆病で懐疑的だった彼が、旅を通じて勇気と探求心を獲得していく過程は、一種の教養小説(ビルドゥングスロマン)としての深みを持っている。
ところが映画では、サクヌッセム伯爵という外的な脅威が前面に出ることで、こうした内面的な成長の描写が後景に退く。弟子のアレック(映画版のアクセル)は、最初から勇敢で前向きな青年として描かれ、大きな変化を遂げることはない。彼は「成長する主人公」ではなく、「冒険するヒーロー」なのだ。
また、原作の科学的啓蒙という側面も弱まる。ヴェルヌは地質学や古生物学の知識を物語に織り込み、読者を教育しようとした。しかし映画では、こうした説明的な要素は最小限に抑えられる。観客が求めているのは知識ではなく、スリルだからだ。
現代の目から見た「殺人事件」の意味
2025年の視点から振り返ると、この改変は興味深い意味を持つ。
現代のエンターテイメント作品、特にハリウッド映画は、ほぼ例外なく明確な「敵」を設定する。マーベル映画には必ず強大な悪役がいる。『ジュラシック・パーク』でさえ、恐竜という自然の脅威に加えて、人間の悪意(ネドリーの裏切り)が描かれる。
つまり、1959年の『地底探検』が行った改変は、現代まで続くハリウッド映画の基本文法の確立過程だったと言える。「純粋な冒険」だけでは商業的に成立しない。そこに「人間ドラマ」と「道徳的対立」を追加することで、初めて大衆的な娯楽となる——この方程式は、今も変わっていない。
しかし同時に、失われたものへの郷愁も感じる。敵のいない冒険、純粋な好奇心だけで突き進む探検、知識の共有を喜ぶ科学者たち——そうした19世紀的な理想主義は、もはや映画的に成立しないのだろうか。
改変の技術——どうやって「殺人」を挿入したか
脚本家の視点から見ると、この改変は見事な技術だ。
原作の物語構造を大きく変えることなく、ゲタボルグ教授という新キャラクターを挿入する。彼を殺害することで、サスペンス要素と道徳的動機を同時に導入する。そして彼の未亡人カーラを探検隊に加えることで、ロマンス要素と感情的な深みを付与する——これらすべてが、一つの改変(殺人事件の追加)から派生している。
しかも、この改変は原作の基本プロットを損なわない。リンデンブロック教授がサクヌッセムの手がかりを発見し、アイスランドへ向かい、地底世界を探検し、生還するという大筋は変わっていない。変わったのは、その旅の「意味」なのだ。
これは、脚本術における「最小限の改変で最大限の効果を得る」という理想的な手法だ。原作ファンを大きく裏切ることなく、映画的な面白さを追加する。チャールズ・ブラケットとウォルター・ライシュの脚本の巧みさが、ここに表れている。
エピローグ——冒険の意味の変容
結局のところ、1959年の『地底探検』における「殺人事件」の追加は、19世紀から20世紀への価値観の変化を象徴している。
19世紀の冒険は、個人の知的好奇心と勇気の物語だった。20世紀の冒険は、善と悪の対立、正義の追求の物語となった。そして21世紀の今、私たちはどちらの冒険も懐かしむ。
ゲタボルグ教授の死は、映画に緊張感とドラマをもたらした。しかし同時に、ヴェルヌが描いた純粋な驚異の感覚を少し損なってもいる。
店を閉めた後、一人で古い映画を観ながら、私はそんなことを考える。もし今後、『地底旅行』をリメイクするなら、制作者たちはどんな「敵」を用意するだろうか。きっと、もっと複雑で、もっと現代的な悪役が登場するに違いない。
そして私は、1959年のシンプルな殺人事件が、意外に洗練されていたことに気づくのだ。


コメント